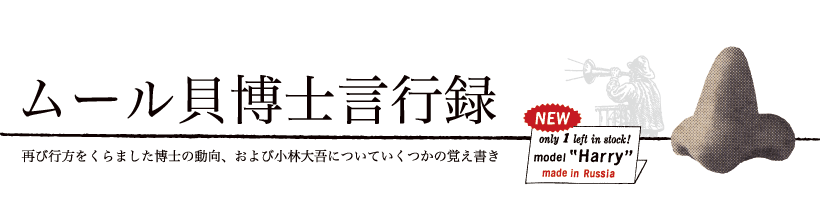3016年2月2日金曜日
2025年6月27日金曜日
アグロー案内 VOL.9 リリースのお知らせ
ふと、VOL.6 が5ヶ月ぶりのリリースで告知から配信まで2週間しかなかったことを思い出します。別に気にもしてなかったけど、今回はほとんど8ヶ月ぶりです。いったい何をあんなにあたふたしていたのか、しみじみ大らかになったものだとおもう。
VOL.7 のときは告知から配信までがさらに短くなり、10日しかなかったのだからわれながら驚かされます。
それどころか VOL.8 のときはさらに短くなり、気付けば配信まで7日しかありませんでした。改めて告知を読み返すと「VOL.7の比ではない」みたいなことが書いてあります。さすがにこれ以上短くなることはないだろうとぼんやり考えていましたが、いま思えばまだまだ青かったと反省せざるを得ません。
何しろ VOL.9 の配信日は7月2日(水)です。
5日後。
念のためお断りしておくと、どこまで短縮できるかチャレンジみたいなことは、VOL.6からまったくしていません。気づいた後で毎回のように「あれ!?」と目ん玉が飛び出しています。どうしてこんなことになっているのか、本人たちにもさっぱりわからない。しかしここまでくるとさすがに事実であっても全然そう見えないので、次回は逆に意識するようになるはずです。ただ、ふつうに忘れるからなあ…。
ともあれ VOL.9 です。
もとより告知のない人生なので、本来であればトラックリストの1文字目から公開していきます!最初の文字は「魚」です!とかそんな感じでだらだらと小刻みにいつまでも更新しつづけていたはずですが、そんな猶予もありません。もう一度にぜんぶ出してしまうしかない。
しかしとりわけ今回はリリース前からタイアップの件があったりして目まぐるしかったので(これも計算ではなく結果としてそうなっています)、そのあたりから話し始めるとキリがありません。リリースまでの日数への言及だけですでに投稿の大半を占めています。
なのでそれらはまたのちのち釈明のようにお話しするとして、今日はジャケット、配信開始日、そしてトラックリストでシンプルにまとめておきましょう。
総じて VOL.9 はいつになくアグロー案内的である、と僕はすごく感じています。楽曲以外のもろもろを含めた、すべてがです。ここまでやってきたからこそ成立することのオンパレードであり、誰かと誰かをくっつけてもここまで多くを賄うことはできません。どうかどうか、楽しんでもらえますように!
2025年6月20日金曜日
ムール貝博士のパンドラ的質問箱 その456
いきなりステッキさんからの質問です(ペンネームはムール貝博士がてきとうにつけています)
Q. 「こんなに頑張ったのに報われない」と思った時に投げ出さず正気を保つ方法を教えて下さい。
たしかに僕らの日々は、費やした労力に対して報われないことのほうが多いですよね。え、そんなことないよ以前はわたしもそう思ってたけど諦めなければ必ず報われるから!と言う人は初めから恵まれたあちら側にいることに無自覚なので、何をしようと一向に報われない僕らの徒労など知るよしもないでしょう。
しかしがんばれば報われるという期待がそもそも人間特有の感覚であって、多くの生物にとってはそうではありません。
百獣の王たるライオンを例にとってみましょう。
王とて腹は減るので日々狩りに勤しんでいるわけですが、毎回必ず獲物にありつけるわけではありません。本気を出して、全力で向き合って、なんなら普段よりはるかに粘ったにもかかわらず、収穫がゼロの日もあります。王であるにも関わらずです。なぜ王なのに空腹をこらえているのか、王であるならなおのこと、腑に落ちないものがあるでしょう。
しかしライオンにとっては、どうあれいつでも、捕食できるかできないかです。がんばりは関係ありません。こんなにがんばったんだからガゼルの1頭くらい食えたっていいじゃないか、と僕らなら愚痴りそうですが、愚痴る甲斐もないことを、ヒト以外の生物はよく知っています。それで腹が満たされるわけではないからです。
ヒト以外の生物にとって、行動と対価は結ばれていません。望んだ結果になるか、ならないかしかない。ではなぜヒトだけが行動に対価を求めるのかといえば、それは僕らが資本主義にどっぷりと浸かりきっているから、と言うほかありません。報われないという考えかたはまさにその弊害もしくは副作用と言えるでしょう。
もちろん、報われる日もあります。それはヒト以外の生物も同じです。しかしそれはがんばったからではありません。必要からくる行動にはいつだって全力でがんばっているのだから、がんばりは理由にならない。なんだかよくわからないがとにかく上手くいった、というだけです。
なので報われると期待することを、まずやめてみましょう。徹頭徹尾、僕らは報われません。報われる人もいるけれど、それは報われる星に生まれついた人であって、僕らではない。人生は不平等と不公平のオンパレードです。もし報われたと感じたなら、がんばったんだから妥当なことだと考えるのではなく、宝くじに当たったようなものとして全身全霊で喜びを表現しましょう。僕らが報われることなど今も昔も、そしてこの先もほとんどないのです。
言うまでもなくここには、悲しみがあります。しかしその悲しみを噛みしめれば噛みしめるほど、人生には味が出るものです。よろしくやってる恵まれた連中には中指を突き立てておけばよろしい。
A. そもそも僕らは報われる星に生まれついてはいないのです。
*
質問はいつでも24時間無責任に受け付けています。
dr.moule*gmail.com(*の部分を@に替えてね)
その457につづく!
2025年6月13日金曜日
ムール貝博士のパンドラ的質問箱 その455
洗濯機フライドチキンさんからの質問です。(ペンネームはムール貝博士がてきとうにつけています)
Q. 来年2月に第2子が産まれます。家族で相談した結果なのですが、半年間の育休をとることに罪悪感があり、職場での立場も悪くなりそうだという予感がしています。人事や上司に伝えるときは吐き気がしそうでした。家族との時間を大切にしたいという気持ちも強いのですが、そのような不安に駆られ、育休の間も精神不安定になりそうな気がします。このような状態をどう乗り越えればよいのでしょうか。
なるほど、これは切実な問題です。ご質問にある来年2月とは今年2月のことなので、梅雨入りを果たした今ごろ何言ってやがるとお思いでしょうが、どうあれ考えることはそれだけでとても大事なので、考えてみましょう。
本来であれば1ミリも抱く必要がないはずのこの罪悪感に、よくもわるくも日本らしさがたっぷりと詰まっています。それゆえに育休の取得に二の足を踏む人や、実際に断念する人が今も数えきれないほどいるはずです。
そう考えると勤務先が育休を制度として導入して実際に取得できること、そしていろいろと思うところはありながらも取得を選び、申請した洗濯機フライドチキンさんをまずは全力で讃えるべきだと、僕なんかはおもいます。すごい!
罪悪感については、必要ないと頭では理解していても抱いてしまうのはしかたありません。実際のところ日本人とはそういう民であり、日本とはそういう国です。
だからこそ、洗濯機フライドチキンさんの決断には、計り知れないほどの大きな意味があります。家庭にとっても、勤務先にとっても、そして社会にとってもです。
なんらかの後ろめたさが拭えないのは、それが当たり前の社会では全然ないからです。そして誰もが二の足を踏み、断念するとすれば、永遠に当たり前の社会にはなりません。わざわざ強調するのもバカバカしい気がするけれど、いつでも誰かが一歩を踏み出す必要があるのです。
初めて月面に降り立ったアームストロング船長の有名な一言を思い出してください。
“That’s one small step for a man, one giant leap for mankind.”(一人としては小さな一歩ですが、人類としては偉大な飛躍です)
これは日本において育休を取得した人にも当てはまります。大袈裟でもなんでもなく、一人が一歩を踏み出すからこそ後につづくことができるのであり、やがてそれが道になるからです。
いずれ育休を取得することが義務にも近いほど当たり前すぎる社会になり、本人にその気がなくとも周囲や会社に「バカ言ってんじゃねえ、他の人が申請しづらくなるほうが迷惑なんだよ、とっとと申請してこい」と蹴り飛ばされるような時代が来る、そのための礎を今まさに築いていることに、胸を張ってください。
もちろん直接的には家族のため、ご自身のためという認識だとおもいますが、実際には数えきれない多くの後進のためになっています。今はまだ他に人がいないような薄暗い道を罪悪感とともに恐る恐る歩いているように見える、その背中はとてつもなく広くて大きい。どれほど誇らしい親御であることか、生まれて間もないお子さんに懇々と言い聞かせたいくらいです。
道を切り開いてくれてありがとう!
A. アームストロング船長と同じ偉業を成したと考えてみてください。
*
質問はいつでも24時間無責任に受け付けています。
dr.moule*gmail.com(*の部分を@に替えてね)
その456につづく!
2025年6月6日金曜日
天下周知の文具メーカーとアグロー案内のタイアップが実現した話
速報です。
なんと、これと言って音沙汰のない今も局所を集中的に席巻してやまないわれらがアグロー案内と、天に遍く知れ渡るいにしえの文具メーカーDAPHNEさんとのタイアップが実現いたしました。長らく箝口令が敷かれていたので、やっとお知らせできて感無量です。
光栄すぎて卒倒しかけた僕らが今回、全力で応援するのは満を持して世に放たれる神々育成ノート「アポロニカ学習帳」です。
なんでもDAPHNEさんはここ数年、この先の神話を担う世代がSNSや動画サイトの影響で幅広い教養と深慮を身につけにくくなっていることに危機感を抱いており、神々の教育的劣化を食い止めるべく学習ノートの開発に着手したんだそうです。
こうした涙ぐましい理念をとことんまで追求した結果、アポロニカ学習帳は気乗りしない神々の学習意欲を強制的に高めるノートとしてはかつてないほどハイエンドな、そしてまちがいなく古代をリードする学習帳のフラッグシップモデルとなっています。書いたことが片っ端から現実になるとか、シュレッダーにかけて海に投げ捨てても自動で復元するばかりか翌朝には手元に戻ってくるとか、とにかく最新かつ解析不能のオーバーテクノロジーがこれでもかとばかりに詰めこまれていて、単なるホモサピエンスでしかない僕らでさえ、ワンチャン神になれるのではないかと錯覚せずにはいられません。
また一部界隈ではSwitch 2と同じかそれ以上に話題が沸騰しているので、ひょっとしたらすでにご覧になった方々もおられるかもしれませんが、これまでに誰も見たことのないような驚異のグラフィックを実現したテレビCMが天界でも放映されています。映像作品としても息を呑むほどすばらしい、圧倒的なクオリティで天の度肝を抜いたCMをご覧あれ!もちろんアグロー案内の面目躍如たるBGMも 聴 き 流 さ ず に 注 意 深 く 耳を傾けてほしい!
さらにこのアポロニカ学習帳、本来であれば神々仕様なので僕ら人類には縁がないはずの商品なのだけれど、アグロー案内をタイアップに選んでくださったこともあり、今回は特別に下界でも販売されることになりました。何から何まで、至れり尽くせりすぎる!
しかも神々仕様のノートなのに税込2,442円と、米5キロ(2025年現在、備蓄米を除く)よりも圧倒的に安い。僕なら迷わず米5キロを選びますが、米にあまり重きを置かない人にはめちゃオススメ!
もはやいつお迎えが来ても悔いはない、そんな気持ちでいっぱいです。アグロー案内、続けててよかった…。DAPHNEさん、ありがとうございます!
2025年5月30日金曜日
ムール貝博士のパンドラ的質問箱 その454
国破れてパンダありさんからの質問です。(ペンネームはムール貝博士がてきとうにつけています)
Q. 全裸っぽい人と目が合った時に言われて安心する一言を何かお願いします。
とかく人生ではいろんな事態に見舞われます。山が火を噴いたり、空から蛙が降ってきたりすることが現実にあるくらいだから、路傍で仁王立ちの全裸っぽい人と目が合うこともあるでしょう。そんなときに得体の知れない不安に駆られるのも、誰であれ無理からぬことです。
ではもしここでその全裸っぽい人が目の合った人を安心させるために「大丈夫です!心配しないで!」と言ったとしましょう。僕らは安心できるだろうか?
できない、と僕は考えます。なぜなら明らかに、というのは世間的社会的にどう考えても大丈夫な状況ではない上に、全裸っぽい人は自身の装いに他人が不安を抱くことを気遣っているという、極めてアンビバレントな状況に陥るからです。全裸っぽい理由を本人がまったくわかっていない状況よりも、圧倒的に剣呑であると言えるでしょう。安心させるための発言が却って不安を煽る皮肉な構図です。だってぜんぜん大丈夫じゃないもの。
僕らが不安を抱くのは、天災であれスマホがないといった個人的なことであれ、それが日常の想定内に含まれていないからです。規模によってはあっさり解決できることもたくさんあるけれど、解決や受け入れることを要する時点で不安の種になります。ましてや全裸っぽい人は他人です。物理的な被害をもたらさないとはいえ、通り魔と大差ありません。そんな無害な通り魔が何を言えば安心して立ち去ることができるだろう?
いろいろ考え合わせると、月並みだけれど「何見てんだオラァ!」とか「見世物じゃねえぞ!」あたりが結局いちばん効果的なんじゃないかな、と僕はおもいます。なんとなればそれは、全裸っぽい人が見られることを望んでいない(=異常であることを理解している)だけでなく、こちらが何らかのアクションを取る必要がない(=最善の行動は今すぐ立ち去ること)と端的に示してくれるからです。また恫喝的な強い口調は、この状況に抵抗を抱いている、つまり全裸っぽい人が助けを必要とするほど心を折られているわけではないことを示してもいます。総じて「たいへんですね」とか「がんばってください」くらいしか言えないところまで、こちらの印象とそれに伴う不安を一気に弱体化してくれるのです。
重要なのは、全裸っぽい人が心配する必要のない強者であり、かつこちらの日常には何ら関わりがないと認識できることです。そのためには全裸っぽい人自身がとにかく強い口調で追い払うしかありません。もし国破れてパンダありさんが全裸っぽい人になった場合は、この点を心がけてみてください。
A. 「何見てんだオラァ!」がいちばん安心できるとおもいます。
*
質問はいつでも24時間無責任に受け付けています。
dr.moule*gmail.com(*の部分を@に替えてね)
その455につづく!
2025年5月23日金曜日
ムール貝博士のパンドラ的質問箱 その453
ときめき都内一等地さんからの質問です。(ペンネームはムール貝博士がてきとうにつけています)
Q. ここのところ、ろくに読めてもいないのに、新しい本を次から次へと買ってしまいます。「積読」より、もう少し響きの良い、言い訳がましくも行為を正当化できるような言い方はありませんか?
たしかに、定期的に言及されてその度に熱狂的な共感の嵐を呼ぶほど、日本の読書家は未読の本が積まれている状態に対して尋常ならざる罪悪感を抱いている印象があります。
僕が昔からずっと不思議なのは、そもそもなぜ罪悪感を抱く必要があるのか(=行為として正当化する必要があるのか)という点です。
きちんと対価を支払っている以上、煮るのも焼くのも自由です。どう考えてもそこに罪はありません。あるのはあくまで罪悪感であって、罪ではない。ではその罪悪感はどこから来るのか?
読まれるために書かれている以上、読まないのは著者に申し訳ない、という理屈は通りません。なぜなら積読は古書にも適用されるのだし、とりわけ古書の場合は著者に何ひとつ還元されるものではないからです。また、どうあれ読まれることは著者にとって光栄ではあるはずだけれども、それは読む側が言うことではないし、エゴに過ぎません。つまりその罪悪感の対象は著者ではなく、書物それ自体に向けられています。
ここでひとつ興味深い事実を指摘しておきましょう。
積読は「tsundoku」として、Cambridge English Dictionary に記載されています。つまり「kawaii」や「emoji」などと同じく日本由来の概念であることが明確に示されているわけですね。
またBBCにも、積読について書かれた海外視点の記事があります。
→英語版
→日本語版
英語の辞書に掲載されたり、英語の記事になるということは、それが英語圏でも共有できる概念だからです。一方で、積読がtsundokuとしてそのまま英語になるということは、この概念がそれまでなかったということでもあります。
BBCの記事では積読を「本を読みたいという志向と、その結果として思いがけず生まれるコレクション」と定義しています。しかしそれならわざわざ正当化を試みる必要はありません。結果として蔵書になっただけだからです。
同じ記事では別の考え方として「散漫な彼氏」という類推を挙げています。隣に恋人がいるのにすれ違った別の誰かに気を取られる人、ということですね。正当化の必要がある点で、どちらかといえばこちらのほうがしっくりきます。
にもかかわらず英語にはその概念がなかった、というのがポイントです。「人ならともかく、書物のような無機物に罪悪感を抱くことがほとんどなかった」と言い換えることもできるでしょう。ではなぜ日本においては読書家の多くが無機物のありように心を寄せるのか?
これはまさに特有と言っていいと思うけど、日本は実体であれ観念であれ、ありとあらゆるものを擬人化する文化があります。ここ数年でいうと主にトチ狂った天候や寒暖差で言及される「令和ちゃん」なんかがそうですね。
そしてそれは、ありとあらゆるものに神が宿るという日本古来の考え方に通じている気がするのです。付喪神なんかはまさにそうだし、不可解な現象に対する解釈としての妖怪もその延長でしょう。つまり日本では形の有無に関わらず森羅万象に対する敬意、ひいてはある種の強迫観念が他の民族よりも強い、ということです。
本来であれば読まれるべきであるはずなのに読まれず積まれた書物に対する罪悪感、もしくは強迫観念がこれまで他の文化圏になかった理由がここにある、と僕は考えます。僕らは「書物の一冊一冊に宿る神さまに引け目を感じている」のであり、それは形を変えた古い信仰の発露でもあるのです。
だとすれば積読の正当化は「気にしないでいい」という点でむしろ不敬である、と言うことができるかもしれません。必要なのは読みたいという気持ちを放擲せず抱き続けることであって、読まないことの正当化ではない。書物の神さまがどちらに納得するか、考えるまでもないはずです。
したがって僕の回答としては本を読めずに積んでおくことの正当化を不要と断じた上で、こういうことになります。
A. 神棚を作ってそこに買った本を積んでいきましょう。
ちなみに僕も相当な数の本を積んでいますが、これはこれでいいのだと自分を納得させたことはありません。全身全霊で、じぶんの不甲斐なさを受け止めています。でも人生ってそういうもんじゃないですか?
*
質問はいつでも24時間無責任に受け付けています。
dr.moule*gmail.com(*の部分を@に替えてね)
その454につづく!
登録:
投稿 (Atom)