ござるござるもニンのうちさんからの質問です(ペンネームはムール貝博士がてきとうにつけています)
Q. 気づけば学生時代に仲の良かった友人とはすっかり疎遠になりました。人間関係もちゃんとメンテナンスしないと縁って切れていってしまうものですね。恋人をつくるにはマッチングアプリ、知人の紹介などアイデアはありますが、友人をつくるにはどうしたら良いのでしょうか…。友人の作り方 と検索したりして虚しくなっています。
これはなかなか剣呑な問題です。質問のすべてがクリティカルにぶっ刺さります。そもそも疎遠になるような学生時代の友人が存在していたかどうかすら疑わしい僕のほうがよっぽど剣呑と言わざるを得ません。
しかし老境の先輩方の行く末を知る機会がじわじわ増えゆくのっぴきならないお年ごろでもあり、僕としても避けて通ることはできない問題という自覚はあります。ひっそりとまとめてひとり胸のうちに収めていた秘蔵のメモをここに開陳しましょう。
まず、人生において友人の多い人と少ない人では、対人距離が明確に異なります。前者が友人と認識している距離感は、後者にとって知人の距離感です。そして後者が友人と認識する距離感は、前者にとって親友の距離感です。友人が少ないと自認する人は友人判定の距離が比較的もしくは著しく狭い、と言い換えてもよいでしょう。僕なんかはまさにこのタイプなので、友人の多い人の友人の話を聞いていると「それは…友だちなの…?」と困惑することがちょいちょいあります。
したがって、知人をすべて友人という認識に置き換えること、これがステップ1です。べつに友だちじゃないけど…と深く考える必要はありません。むしろ固定観念による無意識の線引きを取っ払うことに意味があるのです。いや、上司とか同僚とか部下とかご近所さんとか取引先とかお客さんとかあるじゃん…と思うかもしれませんが、こうしたカテゴリーのひとつとして並列に友人があると考えるところに落とし穴があります。というか何なら僕らはすでにその穴の底にいます。友人とはあくまで、そして常に結果論であって一方的に認定するものではないという、人によっては当たり前すぎることを友人の少ない僕らは改めて自らの認識に上書きする必要があるのです。
ステップ2は「好奇心」です。外界の事象に対する「わ〜おもしろそう!」という気持ちを、観葉植物のように育てましょう。興味をもったら深く考えずに足を運びます。ただし、友人をつくるためではありません。ただただ、自分がたのしむためです。どうもその繰り返しが結果的に人生における肝となるらしい、と先輩方から学んだ今の僕は感じています。そして機会があれば自ら積極的に話しかけていきましょう。ひと昔前の僕なら「むり」と即答していたと思いますが、ここだけの話、歳を重ねるとそうも言ってらんねえわとならざるを得ません。友人の少ない僕らはこの問題について「一本釣り」みたいな印象を抱きがちですが、実際にはそれは「引網」なのです。こうして語る何もかもがぜんぶ自分にぶっ刺さって瀕死の僕が言うんだから間違いありません。
A. 好奇心という引網を担いで、ところかまわず出歩きましょう。
*
質問はいつでも24時間無責任に受け付けています。
dr.moule*gmail.com(*の部分を@に替えてね)
その441につづく!
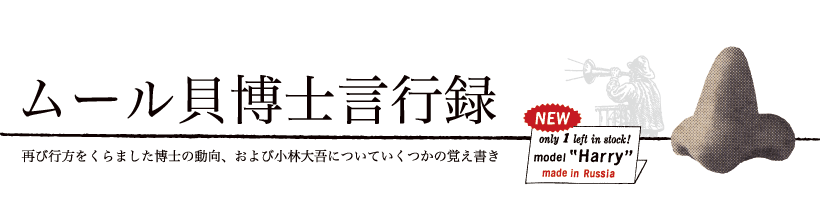

0 件のコメント:
コメントを投稿