それにしてもしみじみとこう、ありがたいことだなあと噛みしめずにはいられないのです。何しろ、今年は何があったっけな、とブログを振り返ってみればほとんど質問箱しかありません。冷静に考えたらそりゃあそうだろうとしか言いようがないんだけど、さも他人事のようにないのかよと自分で自分にツッコむ始末です。
何かあるだろう、いやあるはずだ、と必死に心のポケットを探ります。「ないわけないだろ、おら、ジャンプしてみろ」とカツアゲする強面の不良が目に浮かぶようです。
あ、そうだ翻訳大賞……日本翻訳大賞のロゴ作成をお任せいただいたじゃん!文学や出版に携わる関係者のみなさまが一堂に会する懇親会に参加させていただいて、ロゴを作っただけという場違いっぷりにぷるぷると身をすくめながらも、柴田元幸さんや岸本佐知子さんにご挨拶させていただき、あまつさえ懇親会後には数人の方に「小林大吾さんて……あの小林大吾さんですか?」とまるで著名人でもあるかのようにお声がけいただいたりとか、こうして書いてみるとマッチ売りの少女がマッチを擦ったときだけ映し出される幻のようにも思えてきます。万が一気の毒な夢だったとしても、ちょっと夢を見るくらいいいじゃないか別にとキレ散らかしたい。
いやいやそういう話ならブログに書かないわけないじゃないか、えーといつだったかな……と遡ってみても、どういうわけか見つかりません。あれっ書いてなかったかな……書いてないっぽいな……そうか、じゃ仕方ないな……じゃないだろ書けよ。あのな、おまえちょっとそこ座れ、と自分で自分に説教を始める、そんな年の瀬です。ほんとになんで書き残さなかったのか、さっぱりわからない。ブログ自体はきっちり毎週更新していたのでなおのこと意味がわからない。
ここでやっと冒頭の一文に戻りますけれども、何がありがたいと言って、こんな体たらくにもかかわらず、つまりそれなりに活動しているとはお世辞にも言い難いだけでなく活動したことすら忘れる有様にもかかわらず、年に一度あるかどうかも定かではないようなライブイベント「アグローと夜」をカズタケさんと共に今年もぶじ開催できたこと、小規模とはいえ完売御礼と相なったことです。ありがとうありがとう。20年近くお付き合いいただいている方もいれば、今年アグロー案内を知ったその流れでご参加いただいた方がいたり、宮城から駆けつけてくれた高校生男子がいたり、どう考えても身に余る光栄と言うほかありません。斜陽とか以前にそもそも夜明けがきた記憶も別にない仮死のような活動実績からすると、当たり前ではないどころかむしろ奇跡に近いものがあります。これをありがたいと言わずに何と言いましょう。
とりわけ今年のアグローと夜では、ちょうど1年前の今日、ここで思いの丈をぶちまけた珠玉のせんべい「雷光」の来場者全員分の提供を、ひざつき製菓さんから直々にオファーいただくという、空前にして絶後のサプライズも忘れることはできません。ひざーるくんに扮したうちの人の活躍もあってタケウチカズタケと小林大吾がゲストになりかけたほどです。もう死ぬまで語り継ぎたい。
それでなくともアグロー案内は何らかの予告編や何らかのCMを折々に投入するなどして当初から虚実入り混じるプロジェクトです。そこに厳然たる現実が殴り込みをかけてくるのにも似た、地球に置き換えたら恐竜が絶滅するレベルのディープインパクトがあります。
その結果、この規模のイベントでは通常あり得ないほど全国各地へと雷光が伝来したのだから、言うことなしです。まさしく今年の一大事件であったと申せましょう。
2026年は何があるのか、それともないのか、このブログはまだあるのか、気候変動は続くのか、一寸先はいつでも闇だからこそ、その一歩先に明日が待つと信じて、やはりこう言わねばなりません。良いお年を、と。
今年もありがとうー!
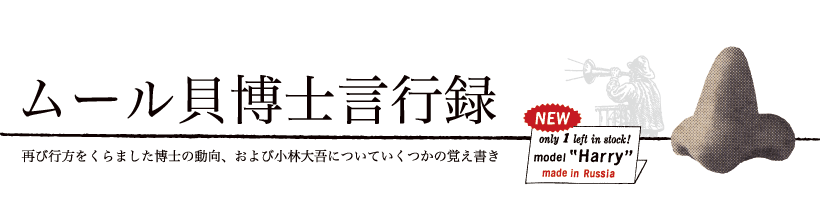

.jpg)







































