3016年2月2日金曜日
2026年1月9日金曜日
電脳的ゲリラ豪雨、あるいは増殖するマネキンがNHKホールを埋め尽くす話
今ごろ何言ってやがるとお思いでしょうが、あけましておめでとうございます。
この年末年始に起きたことといえば、Xのフォロワーが唐突に100人以上増えたのです。べつに大した理由でもありません。2025年に読んだ本でこれがよかったと何気なくポストしたら、たぶん多くのフォロワーを抱えるどこかの誰かに捕捉されてほんのりバズり、書名も出版社も伏せておいたのに年が明けたら出版社公式にまで捕捉されてさらにまたすこし伸びただけです。ちょっと気を抜くとこういうことがあるからおちおち二度寝もできない。
認知度高めの誰かに捕捉されたと気づいた時点で「これは読書アカウントでは全然ありません」といちおう追いポストで泥縄的に釘を刺してはみたものの、誰であれ反射でフォローする時というのは直近のポストをちらりとでも見たりはまずしないので、案の定何の効果もありません。
対象がどんな人物であるかを気に留めない向きにとっては耳寄りな情報が流れてくることを期待してフォローするわけだから当然、意に沿わないことに気づき次第、同じように反射でフォローを外していくことになるでしょう。そうなることが最初からわかっているからこそ事前に止めたいのに、どうにもならない歯痒さがあります。
僕としては何もしていないのにただ見限られることを無意味かつ強制的に味わわされるだけです。最終的にガッカリされるためのお近づきを不毛と言わずになんと言おう。それでなくとも個人的な告知や何やらを正面から受け止めてくださる愛すべきフォロワーのみなさまはせいぜい100とか200くらいのはずなのに、マネキンだけが増殖してNHKホールを埋め尽くすくらいの規模になったところでそれがなんだというのだ。なんでもない日にフォローしてくれる1人のほうがどう考えても100万倍ありがたいしうれしい。
しかしまあそんなことを新年早々ぶつくさ吐き散らかしても仕方がないので、ここはひとつ気持ちを切り替えて前向きに、でなければせめてゲリラ豪雨程度に受け止めるのが冴えた大人のやり方でもありましょう。望むと望まないにかかわらず、雨は降るものです。逆にうっかり増えた100人以上の読書系マネキンフォロワーをどこまで維持できるかというチャレンジにピントを合わせ直すこともできるし、何ならこれが今年の抱負になります。ゴールに向かって突き進む日々のなんと晴れ晴れしいことか!いつになく前途洋々たる1年の始まりです。めざせプラスマイナスゼロ!
こちらからは以上です。本年もこの調子でどうかひとつ、よろしくお付き合いくださいませ。
2025年12月31日水曜日
日本翻訳大賞のロゴ作成をお任せいただきました!とアピールすることを半年以上忘れていた話
それにしてもしみじみとこう、ありがたいことだなあと噛みしめずにはいられないのです。何しろ、今年は何があったっけな、とブログを振り返ってみればほとんど質問箱しかありません。冷静に考えたらそりゃあそうだろうとしか言いようがないんだけど、さも他人事のようにないのかよと自分で自分にツッコむ始末です。
何かあるだろう、いやあるはずだ、と必死に心のポケットを探ります。「ないわけないだろ、おら、ジャンプしてみろ」とカツアゲする強面の不良が目に浮かぶようです。
あ、そうだ翻訳大賞……日本翻訳大賞のロゴ作成をお任せいただいたじゃん!文学や出版に携わる関係者のみなさまが一堂に会する懇親会に参加させていただいて、ロゴを作っただけという場違いっぷりにぷるぷると身をすくめながらも、柴田元幸さんや岸本佐知子さんにご挨拶させていただき、あまつさえ懇親会後には数人の方に「小林大吾さんて……あの小林大吾さんですか?」とまるで著名人でもあるかのようにお声がけいただいたりとか、こうして書いてみるとマッチ売りの少女がマッチを擦ったときだけ映し出される幻のようにも思えてきます。万が一気の毒な夢だったとしても、ちょっと夢を見るくらいいいじゃないか別にとキレ散らかしたい。
いやいやそういう話ならブログに書かないわけないじゃないか、えーといつだったかな……と遡ってみても、どういうわけか見つかりません。あれっ書いてなかったかな……書いてないっぽいな……そうか、じゃ仕方ないな……じゃないだろ書けよ。あのな、おまえちょっとそこ座れ、と自分で自分に説教を始める、そんな年の瀬です。ほんとになんで書き残さなかったのか、さっぱりわからない。ブログ自体はきっちり毎週更新していたのでなおのこと意味がわからない。
ここでやっと冒頭の一文に戻りますけれども、何がありがたいと言って、こんな体たらくにもかかわらず、つまりそれなりに活動しているとはお世辞にも言い難いだけでなく活動したことすら忘れる有様にもかかわらず、年に一度あるかどうかも定かではないようなライブイベント「アグローと夜」をカズタケさんと共に今年もぶじ開催できたこと、小規模とはいえ完売御礼と相なったことです。ありがとうありがとう。20年近くお付き合いいただいている方もいれば、今年アグロー案内を知ったその流れでご参加いただいた方がいたり、宮城から駆けつけてくれた高校生男子がいたり、どう考えても身に余る光栄と言うほかありません。斜陽とか以前にそもそも夜明けがきた記憶も別にない仮死のような活動実績からすると、当たり前ではないどころかむしろ奇跡に近いものがあります。これをありがたいと言わずに何と言いましょう。
とりわけ今年のアグローと夜では、ちょうど1年前の今日、ここで思いの丈をぶちまけた珠玉のせんべい「雷光」の来場者全員分の提供を、ひざつき製菓さんから直々にオファーいただくという、空前にして絶後のサプライズも忘れることはできません。ひざーるくんに扮したうちの人の活躍もあってタケウチカズタケと小林大吾がゲストになりかけたほどです。もう死ぬまで語り継ぎたい。
それでなくともアグロー案内は何らかの予告編や何らかのCMを折々に投入するなどして当初から虚実入り混じるプロジェクトです。そこに厳然たる現実が殴り込みをかけてくるのにも似た、地球に置き換えたら恐竜が絶滅するレベルのディープインパクトがあります。
その結果、この規模のイベントでは通常あり得ないほど全国各地へと雷光が伝来したのだから、言うことなしです。まさしく今年の一大事件であったと申せましょう。
2026年は何があるのか、それともないのか、このブログはまだあるのか、気候変動は続くのか、一寸先はいつでも闇だからこそ、その一歩先に明日が待つと信じて、やはりこう言わねばなりません。良いお年を、と。
今年もありがとうー!
2025年12月26日金曜日
アグロー案内 VOL.10解説「水茎と徒花/black&white」
KBDG作品は基本的にどれもいろんな意味でラブソングですが、ロマンスを中心にどんと据えたものは多くありません。「水茎と徒花/black and white」はその数少ないうちのひとつです。というか、これと「処方箋/sounds like a lovesong」くらいじゃないだろうか?
とはいえこれまで正規リリースはしておらず、YouTubeでの公開に留まっておりました。ありがたいことにこのスピンオフとして、手紙を食べちゃった側の視点で描かれたtoto嬢の「水茎と徒花と球根/black and white pt.2」、タカツキによるめちゃカッコいいラップ版「徒花と水茎/white and black」があります。
なので公開から10年近くの時をへた、これが初の正規リリースです。鉛筆での拙いイメージラフを、御大タケウチカズタケが鮮やかな4K高彩度フルカラーに仕上げてくれてもう感無量と言うほかありません。なんちゅう美しさだろう。じぶんが虎の威を借る狐に思えてきます。
この曲に関してはそもそもテーマが同じことの繰り返しなので、リメイクというよりもむしろ「相変わらず同じことをやっている」と受け止めるべきでしょう。つまりこれもまた、ささやかな後日譚のひとつなのです。あまりに何度も同じことを繰り返しているので、ふたりともすっかり板についています。
またこれは、僕が音楽を用いずシンプルに詩の朗読をするような機会に恵まれたとき、かなりの頻度で詠む一編でもありました。なんとなれば言わんとするところが100%伝わることが初めから確約されているようなものだからです。そしてそうした機会を重ねれば重ねるほど、手紙を読んでから「食うなよ」までの時間が伸びていきました。ビートがないとこの部分をめちゃめちゃ活かせることに気づいたわけですね。
その後、カズタケさんとの「アグロー案内」が始動し、その実演会でもある「アグローと夜」を数度催したところで、ある日ふと天啓に打たれます。ひょっとしてこれ(水茎と徒花)、カズタケさんとなら朗読で得た知見を完璧に活かせるばかりか、「アグローと夜」でさらにおもしろくなるんじゃないだろうか……?
ライブが不得手なのは今も変わらずですが、それを踏まえてもなおそのために形にしておきたいと思えた、という意味においてこれはおそらく初めての作品です。そして実際、その甲斐はあったと断言してよいでしょう。
そういえば10年前に公開したときはただリンクを共有しただけで何も記していなかった気がするので、タイトルについても改めてふれておくと、「水茎」は筆や筆跡のことで、転じて手紙を意味する言葉です。徒花というのはもちろん、実を結ばない花のことですね。どちらも植物由来でどことなく風情を漂わせながら、かつムダな手紙を完璧に示す、エレガントなタイトルだったと今でも思います。
2025年12月20日土曜日
12年前の馬がとうとう年貢を納める話
そういえば昔、ジゴロという言葉があったのです。フランス語なのでべつに消え失せたわけではないけれど、今それを耳にしてすぐに理解できるのはたぶん中年以降、何なら初老以降の世代でしょう。正直、僕ですらリアルタイムではないというか、目にしたことはあっても耳にした記憶はありません。日本においてはもう完全に死語です。僕が生まれたころにはまだギリ生きていたくらいの言葉なんじゃないかとおもう。
なので12年前でも当たり前に死語だったはずですが、にもかかわらず深く考えずに臆面もなく年賀状キャンペーン応募時のキーワードとして採用していたことに今ごろ海より深く反省している次第です。
そんなおっさんの後悔はさておき、12年前の午年における年賀状図案はこんな感じでした。
実物が手元になく、ブログから引っ張り出してきたので画質は劣悪ですが、イメージが伝わればよいので概ねこんな感じです。当時はまだ印刷を外注せず、自らせっせと刷っていたことが懐かしく思い出されます。時代の流れで昔ほど簡単ではなくなってしまったので、感慨もひとしおです。ライト部分に2014と記されています。
別にこんなのすっかり忘れて新たな図案をひねりだしてもいいのだけれど、でももしこれをやるならさすがにこのタイミングしかないよな、ということで、2026年の図案はこうなりました。めでたい!
今年もまた言葉にならないヘビー級の感謝をこめて、この年賀状を若干名にお送りいたします。
ご希望のかたは件名に「年貢の納めドキッ」係と入れ、
1. 氏名
2. 住所
3. わりとどうでもいい質問をひとつ
上記の3点をもれなくお書き添えの上、dr.moule*gmail.com(*を@に替えてね)までメールでご応募くださいませ。
そして今年も!わりとどうでもいい質問にNG項目を設けます。「二択」は禁止です。そのせいなのか単純に需要がないだけなのか(かなり高い確率で後者)、応募数もだいぶ減少しているのでゲット率が明らかに上昇している事実も改めて明記しておきましょう。
締切は12月27日(土)です。
応募多数の場合は抽選となりますが、複数枚お持ちの方もわりといらっしゃるので、心配は無用です。これまでためらっていたり、初めての方ほどこぞってご応募くださいませ。こう言っちゃなんだけど、想像するほどの需要は20年前からありません。
励ましのお便りやアグロー通信へのメッセージなど、手ぐすね引いてお待ちしております。
今年もありがとうー!
2025年12月19日金曜日
細部をあれこれ補完するポッドキャスト「アグロー通信」のこと
日常的にSNSに触れていると、と言っても別にふと思いついた他愛のないことをぽつりとポストしてるだけで、活用もへったくれもないですけれども、なんとなくもう話した、伝えた、お知らせしたようなつもりでそれっきり、みたいなことがよくあります。実際にはみんながみんな流れ星よろしく飛び去る小さなポストをタイミングよくキャッチできるわけなどないし、そもそもSNSをやっていない人がたくさんいるのに、ついそれを忘れてしまうのです。
そんなこんなでまたうっかり機を逸した感がないでもないですが、おかげさまで今年もぶじ終えることができた「アグローと夜」をタケウチカズタケと共に取り留めなく振り返るポッドキャスト「アグロー通信」が配信されました。
なんと第1回は12月1日に配信されています。光陰矢の如しとはよく言ったものです。たまたま忘れ物があって慌てて取りに訪れた際、お茶などご馳走になったりしてそのついでに録ったとは思えないほど、きちんとおしゃべりしています。何も決めずにただふだんと同じように雑談しているだけとも言えるので、とても楽しそうです。途中から録ってることを忘れてたんじゃないかとおもう。僕らはいつもだいたいこんな感じです。
とにかく気楽な間柄でもあるし、考えてみたらライブのMCやSNS、ブログではまどろっこしいお伝えしきれないことをまるっとお伝えできるので、今後も折を見てぽちぽち更新される予定です。
せっかくの機会なので、もしよかったらメッセージなんかも送ってみてください。
・アグローと夜の感想
・あなたの町の山本和男
・見つけた!ひざつき製菓
・教えて!カズタケ先生
・あったらうれしいアグローCM
などなど、その他なんでもOKです。なんなら甘やかすほど励ましていただきたい。
このブログのコメントでも、メール(dr.moule※gmail.com)(※を@に換えてね)でも、SNSのリプライやDMでも、ありとあらゆるルートで手ぐすね引いてお待ちしております。
とくに反応がないことも全然ありそうなので、僕もアラブの富豪を装ったゴージャスなメッセージを用意しておく所存です。
2025年12月12日金曜日
アグロー案内 VOL.10解説「九番目の王子と怪力の姫君/how he became a pearl diver」②
「九番目の王子と怪力の姫君」は、たぶんあまり類を見ない制作過程をへて完成した作品でもありました。
まず、この曲に関してはテキストが先に書かれています。カズタケさんがトラックの制作にとりかかったのは、彼がそれを読んだあとです。一読して浮かんだそのイメージでトラックを作ってもらった、ということですね。
「紙芝居を安全に楽しむために」や「フィボナッチは鳳梨を食べたか?」も先にテキストが書かれていましたが、これはテキストというよりすでに録音してあった朗読を音楽と組み合わせてもらう趣向(むちゃ振り)だったので、僕からカズタケさんへの往路だけで作品が完成しています。
それにひきかえ、「九番目の王子〜」は後でリーディングをビートに嵌めることが前提でした。つまり、このテキストがビートにどう乗るのかさっぱりわからんけどとにかく書いてカズタケさんに読ませる、そしてこのテキストがビートにどう乗るのかさっぱりわからんけどとにかく浮かんだイメージでビートを組む、というお互いに五里霧中の状態で制作が進められたのです。
ビートを意識せずにテキストを書いてから乗せ方を考えること自体は、初めてではありません。以前からちょこちょこと試していて、たとえば「前日譚」とか「魚はスープで騎士の夢を見る」なんかもそうです。ただこれらは先にトラックがあったので、僕がテキストをその雰囲気に寄せて書いています。「九番目の王子〜」はここが逆です。これまではまずカズタケさんが球を投げる側にいたのが、今回は僕が投げる側に回った、と言えばわかるだろうか。
いずれにしても、ビートを意識せずに書かれたテキストでもビートに嵌めて読むことができる、という確信がなければ不可能なプロセスです。BPMが60だろうと100だろうと一向に差し支えない点で、これはリーディングというスタイルの真骨頂とも申せましょう。
僕の胸を瞬時に射抜くようなめちゃ素敵なビートが送られてきたので、あとはリーディングを乗せるだけです。適当に書き散らかしたテキストの細部を、ビートに合わせて整えていきます。ある程度のまとまり、具体的には8小節くらいのイメージでテキスト全体を区切っていくわけですね。8小節という単位は、それが曲の構成としてごく一般的な区切りのひとつだからです。その際、テキストの多かったり少なかったりする部分を削ったり補ったりもしていきます。
ところが、よし、大体こんなもんだな、と整え終えて、いざ乗せようとしたところで思いもよらない壁にぶち当たりました。
8小節分のリーディングを終えても、まだビートが一段落しないのです。テキストの区切りを間違えたと思って指折り数えても、やっぱりちゃんと8小節で区切っています。ということは…
このトラック、10小節でループしてる…!!!
そんな次第で、整えたテキストをまた一から区切り直すことになったのです。まさかこんなところで通常とは異なる構成が施されていたとは想像もしておらなんだ。
ちゃんと聴きながら区切らんといかんな、と改めて反省したものの、そもそもトラックに合わせて書いたものではないので、トラックの構成とテキストの構成には当然ズレが生じます。なのでやむなく便宜的に僕がトラックを組み替え、リーディングを乗せました。とにかくまずはリーディングを乗せることが肝要だったし、むしろ構成についてはまた調整をお願いすればいいと考えたからです。そして僕としても意外なことに、その組み替えがそのまま採用されています。
シンガーやラッパーが受け取ったトラックを自ら組み替えることなど、本来はまずありません。便宜上とはいえそれができるのは、どうあれ僕がトラックを自作してきた経験があるからです。したがってこの制作過程ひとつとっても、この2人でしか成し得ない、ひいてはめちゃアグロー案内的であるとも言えるわけですね。
でも実際に仕上がって聴いてみるとむしろ初めからこの着地を目指していた気がするくらい、しっくりきています。ふしぎなもんですね。もし8小節ループだったらどうなってたんだろう?
「九番目の王子と怪力の姫君」はこんな作り方もあると実感できた点で、おそらく一生忘れ得ない作品のひとつです。
登録:
コメント (Atom)
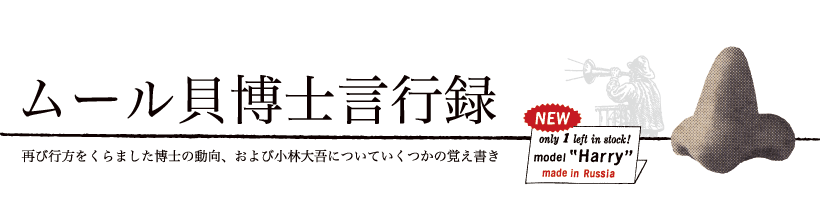


.jpg)








