急がばハーレーさんからの質問です。(ペンネームはムール貝博士がてきとうにつけています)
Q. 最新作の言葉選びが「すでによく知っている小林大吾」を強く感じるものでした。生成AIに小林大吾的なワードセンスを盛り込んで作らせたものを起点に創作するみたいな実験でもしているのだろうかと。そこで質問です。AI小林大吾とリアル小林大吾の決定的な相違点を教えてください。
肉体ですね。(キッパリ)
しかしまあ、この場合はたぶん脳みそとの比較だとおもうので、 その前提で考えてみましょう。
現在の生成AIは天文学的な量のデータを駆使する「模倣」が主です。言ってみれば、この状況ではこう対応するという、それこそミクロからマクロまでありとあらゆる事例の学習と試行錯誤を日々とんでもないスピードで繰り返しているわけですね。今では扱えるデータ量が実質的に無尽蔵なこともあって、将来的には自我を持つようになるんじゃないかと感じてしまうほどの精度に達しつつあります。
ただ、90年代からAIを専門としてきた知り合い曰く(なんかデマの拡散時みたいな書き方だな)、AIがいずれ自意識を獲得しないとは言い切れないけれども、そのためにはまだ別のアプローチによるさらなるブレークスルーが必要なんだそうです。猫がどれだけ経験を積んでもライオンにはならないのと同じような認識なのかもしれません。
模倣の繰り返しだけでは意識には到達し得ない。
他愛のないよもやま話の一環だったので、ここまでの話の科学的な妥当性についてはひとまず置いておきましょう。とりあえず彼がシンプルにまとめてくれた話から僕個人がそう認識した、というだけです。
僕がここで言いたいのは、上記の話からふと浮かんだ、「人間の意識や精神活動が模倣に基づくものではないとなぜ言い切れるのか?」という疑問です。この疑問を実際にぶつけてみたんだけど、ウムムムと2人で唸っている間に時間切れとなってしまったため、今のところ結論は出ていません。
僕らはもちろん、日常的に自ら考え、自ら判断し、自ら行動しています。しかし生まれた瞬間から「今日はどの靴を履こうかな」とか「推しが結婚とか超ショックなんだけど」とか「高裁の判決には事実誤認があるのではないか」みたいなことを考えたりはしません。これらの思考はすべて、できたてほやほやの脳が肉体の成長と共に多様な学習を重ねた結果です。
しかしここで言う生物にとっての学習は結局のところAIの学習と本質的にはそう大差ないのではないか、という印象を、今の僕は抱いています。なんとなれば精神活動もまた、膨大な数の神経細胞同士の結びつきと電気的な信号のやりとりの集合であり、別の個体を模倣するのは明確な判断基準がある点で合理的な生存戦略でもあるからです。
そう考えると、レベルとか段階の違いはあっても決定的な不変の相違点はないようにも思えてきます。というか、仮にAIとの相違点があっても区別がつかないなら、それはないのと同じです。
と打ち遣るのも何なので、しいてひとつ挙げるとすれば新しい要素を取り込む可能性が常にあることかもしれません。たとえばエロとかグロとか、卒業をテーマにした「桜」というタイトルの詩を書くとか、原則として一人称を使わないという長年のマイルールを変更するとかです。マイルールなんだから僕にとっては任意ですが、模倣するAIにとっては規則になります。それを放棄できるのはオリジナルである僕だけです。
ただし、ほどなくしてAIも一人称を使うようになったりエロいことばっかり言うようになるのでやっぱり区別がつかなくなるし、それでなくとも「実在したんですね…」って言われたことが今までに3回くらいあることを考えると、もうAIでいいじゃないともおもいますけど。
今これを書いてるのだって、AIかもしれないですよ。
A. 本人の気が変わる可能性が常にあります。
*
質問はいつでも24時間無責任に受け付けています。
dr.moule*gmail.com(*の部分を@に替えてね)
その438につづく!
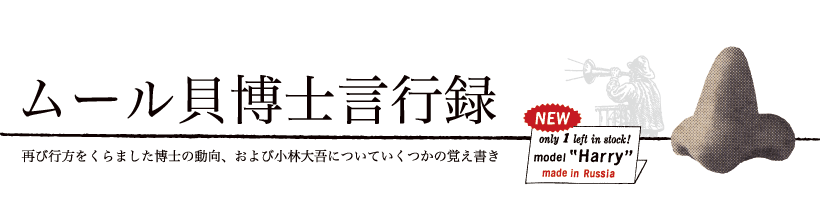

0 件のコメント:
コメントを投稿