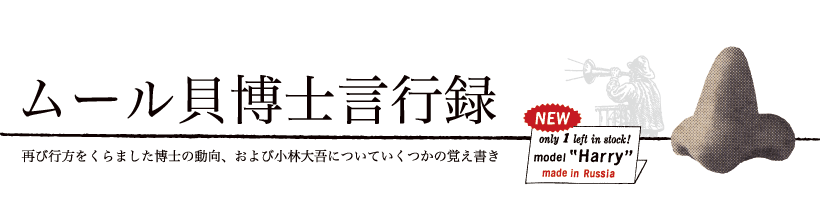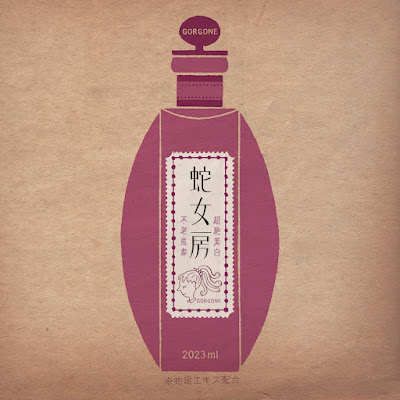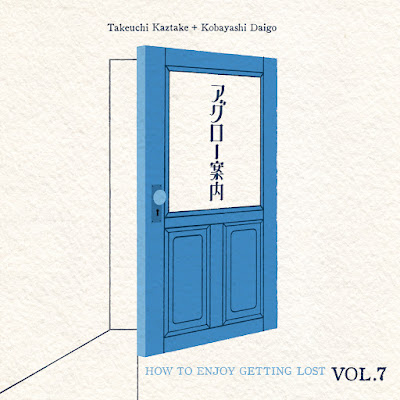ことの発端は、見たことのない煎餅をたまたまスーパーで見かけたうちの人が買って食ったことにあります。「閃光の如く旨味が走る」というマッチョでドスの効いた惹句の通り、ひと口で閃光に舌と脳髄を貫かれてしまい、それからずっと飢えた獣のように血眼でいるのです。
もちろん、また買えばいいんだからふつうは血眼になる必要はありません。ではなぜこんなことになっているかといえば、あちこち探し回ってもなかなか見つからないからです。
最初に見かけたスーパーにいそいそと買い足しに出かけて、「広告商品だったのでもうありません」と言われたときの、奈落に突き落とされたようなうちの人の絶望を想像してみてください。あわてて思いつくかぎりのスーパーを十数店駆け巡るものの、これがまたどこにも置いていないのだから、進退極まるとはこのことです。血眼から真っ赤な涙が流れるのも無理はないし、ジェダイが暗黒面に堕ちるとしたらまさにこんなときだろうと痛感せずにはいられません。
ネットでいいじゃんとお思いでしょうが、直営のオンラインショップやその他のサイトで売られているのは1セット16袋であり、気軽に買うには多すぎます。何しろひと抱えもある段ボールでドンと届くのです。煎餅くらい、もうちょっと気楽に買いたい。
というようなことをお店でお客さんに話していたら、そばにいたうちの人がバツの悪そうな顔をして言うのです。「もう注文してしまいました…」
背に腹は代えられません。ほどなくしてうちに16袋入りの段ボールが届きます。すぐに食べ切れる量でもないので、布教のためにせっせと知人にお裾分けしていきました。アグロー案内の片割れであるタケウチカズタケもその一人です。
そして僕が先月の「アグローと夜」でこの話をし、みんなでふむふむ、そんなら一度買ってみよ、と思ったらまじで生活圏のどこにも売ってない、というわけでひと月以上が経過した今もまだドタバタと探索劇が繰り広げられているのです。
おそらく、すぐに手に入るものならとうにほとぼりも冷めていたでしょう。そしてまったく売られていないならあきらめもつくのに、じつはそうとも言い切れず、あるところにはあるらしいから困るのです。そして運よく雷光を射止めた人々はやはりもれなく閃光に貫かれていることがまた、この状況と焦燥に拍車をかけています。煎餅リテラシーのほとんどない僕ですら、あれは美味しいと本当におもうし、うちの人が煎餅ソムリエと崇める古書店仲間もびっくりして太鼓判を押すくらいなので、見かけたら即買いでまず間違いありません。
僕も相当の範囲であちこち駆け巡っているつもりですが、最初に見かけたとき以来、今も実店舗では巡り会えていません。ひざつき製菓の煎餅にはちょいちょい出会うようにはなりましたが、雷光はない。ついでに言うと「城壁」もない。
ちなみに栃木のメーカーなので、栃木近郊ではわりと難なく手に入るそうです。まだそこまで広く浸透しているわけではないとも言えるけど、むしろ一部のメーカーがちょっと幅を利かせすぎなんじゃないのかとおもう。
こうしてSNSや知人、うちの人の古書店ネットワークから寄せられるわずかな手がかりを元に、一縷の望みをかけてあちこち出向いては空振りを繰り返し、あと一歩で出会えそうな、パチンコで言うとあと5000円ぶっこめば出るみたいな根拠のない期待感だけが募るまま、雷光を再び手にすることなく2024年が暮れようとしています。うちにあるのはあと2袋です。とてもじゃないけど、開封できる気がしない。
したがって、今年もいろいろあった気がするけれど、一年をひと言で表せと言われたら雷光の2文字に尽きるでしょう。いったいなぜこんな報われない恋みたいなことになっているのか、つくづく無念と言うほかありません。もう以前と同じ日々には戻れない、そんな気にさえさせられます。今の僕らにできるのはただ、ひざつき製菓の公式キャラクターのはずでありながらLINEスタンプ以外ではまったく見かけない「ひざつきボーイ」のスタンプを日々連打することだけです。おちおち年も越せません。
本来であれば今年はタケウチカズタケとのアグロー案内やその実演版である「アグローと夜」を筆頭に、ドームツアー、海外進出、チャンネル登録者数100万人突破、紅白出場、M-1連覇、テイラースウィフトから直々のオファーが来たりと、そんな夢を見て目が覚めたら朝だった話の数々を、感謝とともにあることないこと振り返っていたはずですが、今となってはそれも儚い、泡沫のようにも思われます。初めからぜんぶ泡沫でなかったとも言い切れませんが、この際それは問題ではありません。
*
ともあれ今年もここでこうして、また来年があることを前提に(←重要)ご挨拶ができるのも、ときどき思い出しては訪れてくれるみなさまのおかげです。アグロー案内を聴いてくれてありがとう。初日と最終日を兼ねたライブに足を運んでくれてありがとう。
何より、10年もの間アウトテイクのまま留まっていた「コード四〇四/cannot be found」のこれ以上ないほど完璧な正規リリースや、当人たちですらまったく想定していなかった「紙芝居を安全に楽しむために」のライブにおける発展形は御大タケウチカズタケの存在なくして語ることができません。とりわけ「紙芝居…」はライブでなんかできるわけないと思っていたのが、今やライブでないと意味がないくらいの域に到達しつつあります。難があるとすればそれほど需要がないことですが、考えてみたら元から需要の多い立ち位置でもないので、今さら気にすることもないでしょう。「コード四〇四」だってここまで一分の隙もなく鮮やかに披露できる日が来るとは夢にも思っていなかった。
僕にまだ少しでも追う価値があるとするなら、それはひとえに彼のおかげです。去年感じたよりもまだもうちょい先がありそうだと心から思える、それだけでもまちがいなくこの1年の甲斐はあったと断言せずにはいられません。
僕が取り返しのつかない何かをやらかさないかぎり、この道はまだ続きます。どうか引き続きもう少し、よろしくお付き合いくださいませ。
今年もありがとう!そしてよいお年を!
あとうちの人を暗黒面から連れ戻すための情報もお待ちしています。