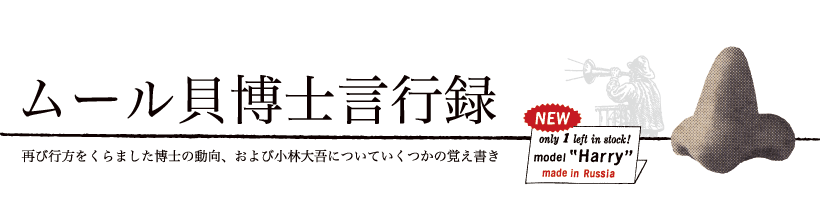キャプテン・クックパッドさんからの質問です。(ペンネームはムール貝博士がてきとうにつけています)
Q. 家族でけんかというほどでもない、意見や気持ちの相違があった時の解決策を教えてください。
きのこの山かたけのこの里かというだけで常にキューバ危機みたいな一触即発状態にあることを考えると、「けんかというほどでもない」が実際のところどれくらいの衝突を指しているのか、具体的な例がほしい気もしますが、それがなくとも考えられそうなことだけ考えてみましょう。
まず、「意見や気持ちの相違」は家族であっても初めから互いに別人格である以上、当たり前のことです。むしろ一致することのほうが例外であり、望外の喜びであると胸に刻むほうが圧倒的によろしいと僕なんかはおもいます。
家庭内にかぎらず同意や共感は誰にとってもうれしいものですが、それに執着すると異論に対する抵抗感はいずれ忌避感に転じます。その先に待つのはどう考えても軟着陸ではありません。ですよね?お互いに歩み寄らないかぎり、着陸は絶対にあり得ない。
それはつまり、こちらだけが歩み寄ってもやっぱり着陸とは言えない、ということです。他者のアドバイスが実際のところほとんど意味をなさない理由がまさしくこの点にあります。どうあれ徹頭徹尾、当事者同士ががっぷり四つで向き合うほかないのです。夫婦間のことならそれができることこそ結婚の最低条件にすればいいのに、といい年ぶっこいたおっさんになった今ではしみじみおもいますが、僕もべつに当時そんなことは1ミリも考えていなかったので、えらそうなことは言えません。
では打つ手がないかというと、そんなこともありません。一番手っ取り早いのは、自分の認識を変えることです。相手の立場を採用してもいいし、押しも引きもせず「なるほど」とそのままどしんと受け止めてもいい。なんとなれば相手に譲歩する気配がないかぎり、できることといったらそれくらいしかないからです。
白旗を挙げるわけではありません。言葉を尽くした上で受け止めて「まあいいか」とおもえるならそれでよし、おもえないならそのままにしておけばいい。自分とまったく同じではない誰かと日々を共にするというのはそういうことです。相手に同意できない自身の認識にブレーキをかけることができないなら、それはつまり自身に都合のよい結果しか受け入れられないわけだから、そもそも解決など望むべくもありません。不倫とかクソめんどくさい話ならまた話は変わってくるけど、「けんかというほどでもない」ならそれほど難しいことではないはずです。
そして経験上、受け入れられないと感じていたことを一度でも受け入れると、びっくりするくらい気持ちが楽になります。自身の認識を堅持することにいったいどれだけの意味があったのか、首を傾げるほどです。
また受け入れる姿勢を見せることの相乗効果として、相手が軟化することもあります。もちろん全然しないことも余裕でありますが、それはもうそういうものとして受け止めるほかありません。何しろ家族ですからね。
A. 自身の認識を改めることから始めましょう。
*
質問はいつでも24時間無責任に受け付けています。
dr.moule*gmail.com(*の部分を@に替えてね)
その444につづく!