トリックオアトリートメントさんからの質問です。(ペンネームはムール貝博士がてきとうにつけています)キューティクルを整えてくれないならいたずらするぞという、西洋の風習のひとつですね。
Q. 子供の頃に学習塾の問題文で読んだ短篇小説が忘れられません。少年2人が夜の海岸で話していて、1人がクラゲを漢字で書くと海月だと言います。もう1人が水母だと言います。主人公はそれを聞いていて、後日両方正しいと知るというだけの話です。誰の何という短篇かは調べても全くわかりません。なんとなく印象的で、忘れられない短篇小説は何ですか?
質問そのものより前段のほうが圧倒的に気になるやつですね。ひょっとして今ならAIが探してくれるのでは…と3種くらいのAIに尋ねてみましたが、やっぱり全然わかりませんでした。なんとも言えない静謐な味わいがあってめちゃ良さそうな短篇ぽいので、ご存知の方がいらしたらぜひご一報ください。
どういう話で何が起きてどんな教訓があるのか、みたいなのよりもこういう、なんだかわからないけどいつまでも忘れられない話は、いいですよね。ぐいぐい引きつけられる超絶ストーリーテリングも大好きなんだけど、しずかに沈殿して血肉になるのはむしろこういう作品なのかもしれないな、としみじみおもいます。
そうだなあ、今パッと思い浮かんだのは、芥川龍之介の「煙草と悪魔」です。先に書いたような静謐な味わいとか余韻は別にありません。共通点を挙げるとすれば、これといって特に教訓はないところです。
ストーリーはシンプルです。キリスト教の伝来に伴って、悪魔が日本にやってきます。もちろん、神を信じる人を誘惑したり唆したりするためです。
ところがまだキリスト教の伝来間もないので、信者がほとんどいません。信者がいないということは、悪魔としても誘惑したり唆す相手がいないということです。
することもなくて暇を持て余した悪魔は、園芸でもするかと畑を耕し、渡来の際に持ち込んだタバコを栽培し始めます。そういう話です。神とか悪魔とか信仰の話ではなくて、タバコの伝来についての話なんですね。悪魔がせっせと畑耕してんじゃないよ。
何がいいって、めちゃポップなところです。上に書いたあらすじだけでもわかるとおもうけど、内容的にはぜんぜん古さを感じません。感じるとすれば文体だけです。加えて、狡猾なつもりでいる悪魔がちょっとこう、バカなのがいいんですよね。
さらに言うと個人的にものすごく印象深い一文があります。「西洋の善が輸入されると同時に、西洋の悪が輸入されると云う事は、至極、当然な事だからである。」という部分です。これを初めて読んだ当時は善悪に西洋も東洋もないと思いこんでいたので、困惑した記憶があります。
話としてはどうでもいっちゃどうでもいい感じなのに、結果としてじぶんの人生哲学に大きく寄与したという点で、忘れられない一遍です。
こうしてみると全然、なんとなくの印象じゃないな。面目ないです。
A. 芥川龍之介の「煙草と悪魔」です。
*
質問はいつでも24時間無責任に受け付けています。
dr.moule*gmail.com(*の部分を@に替えてね)
その468につづく!
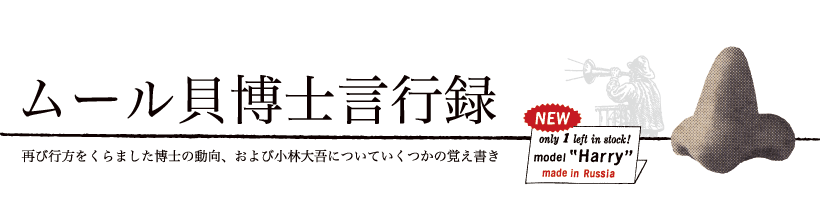

0 件のコメント:
コメントを投稿