カピバラ課長さんからの質問です。(ペンネームはムール貝博士がてきとうにつけています)
Q. 300年後の日本語は今と変化ないと思いますか?
いいですね。僕はこういうことを考えるのが大好きです。
まず大前提として、言葉は日々刻々と変化し続けています。変化が激しいのは主に俗語だけれど、たとえば僕が子どものころは「とりま」という言葉はありませんでした。初めて聞いたときは「『ま』って何?」と困惑したし、ぶっちゃけ今も気になっています。でもこれはたぶん、遠からず辞書に載ることになるとおもう。あるいはもう載ってるんだろうか?
それから僕の手元にある30年以上前の、酷使しすぎて「アスパラギン」よりも前のページが失われている古い広辞苑に、「うざい」という言葉は載っていません。たしかその元の形だった「うざったい」もありません。しかしそれだけ古くても「ださい」と「サボる」は載っているので、たぶん「うざい」もとっくに辞書に載っているでしょう。
では現代でもそれなりに使われているこれらの言葉をむりやりつなぎ合わせて「だせえしうぜえし、とりまさぼりで」というせりふを作ってみます。中二病を患った思春期で体育祭なんかやってられるかみたいなことだとおもえば、まあまああり得なくもありません。僕も書いていてヒエッとなるけれども、どうあれ意味が伝わればそれでよろしい。
その上でこの一言を、300年前の江戸中期に持っていってみましょう。何ひとつ伝わらないのは100%明らかです。語感からして外国語というよりも方言かなと感じる可能性は高いですが、いずれにしても通じません。現代の僕らがたとえば「ふめえしなでえし、ほいなかもりで」と言われて感じるような困惑がおそらくあります。なんとなく日本語っぽいなという気はするものの、さっぱりわからないですからね。
もちろんこれは極端すぎる例です。意思の疎通自体はたぶんどうにかはかれるとおもいます。たぶん、と留保して断言できないのは、単語だけでなく発音の問題もあるからです。現代よりも発音のバリエーションがはるかに多かった1000年前の日本語(や行の「い」もわ行の「ゐ」もあ行の「い」と明確に異なっていたようです)は方言どころか完全に外国語に聞こえるだろうと個人的には考えているので、300年後も音の影響がないとは言い切れません。
以上を踏まえると、お互いにしょっちゅう擦り合わせが必要になるものの、意思の疎通は可能である程度には変化してるんではなかろうか、というのが僕の結論です。「ありがとう」ですら、300年前は使われてなかったはずですからね。
ただ言葉の誤用とか美しさに対して現代は300年前に比べれば社会として圧倒的に意識的だし、こうあるべきという圧力も強いので、過去300年よりもその変化はゆるやかかもしれないなという気もします。
A. 変化の有無で言ったら絶句するほど変化しているはずです。
*
質問はいつでも24時間無責任に受け付けています。
dr.moule*gmail.com(*の部分を@に替えてね)
その445につづく!
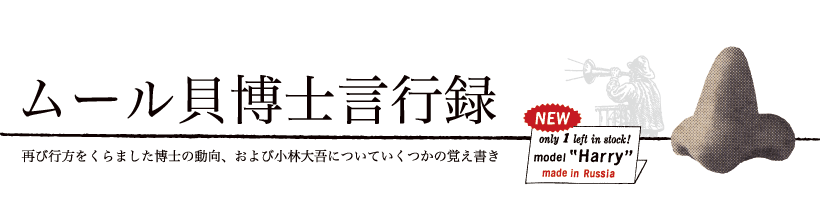

0 件のコメント:
コメントを投稿