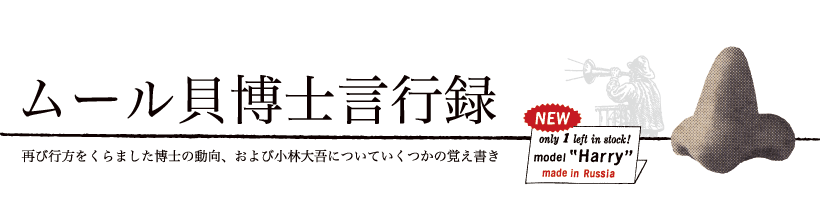3016年2月2日金曜日
2026年2月27日金曜日
ムール貝博士のパンドラ的質問箱 その472
大陸間弾道2歳児さんからの質問です。(ペンネームはムール貝博士がてきとうにつけています)
Q. 「垢抜ける」とか「洒脱」とかイカしたさまを表現するときに言いますが、どうして抜けたり脱したりしているんだと思いますか?
いい着眼点です。ぶっちゃけ、このことを早い段階で一度でも考えるかどうかで、その後の人生が数ミリ変わると言ってもおそらく過言ではありません。
オシャレの漢字表記である洒落にしても落の字が含まれていることを考えると、イカしているとはどうあれ何かが抜け落ちることである、ということになりましょう。何が抜け落ちるかといったらそれはもちろん垢もしくはそれに類する何かなわけですが、ここで重要なのはその欠落対象がオシャレでもなんでもないわれわれではなく、むしろ何らかのアドバンテージを手にしたように見えるオシャレピーポーである、という点です。
生存に関わるレベルでないかぎり、垢を排除しようとする生物はヒト以外に存在しません。それはつまり、垢まみれで小汚いわれわれこそが大多数であり、より自然であるということです。
垢が必要であるとまで踏み込むつもりはありません。どう考えても、別になくてよろしい。しかしゼロにする必要があるかといえば、それは明確にノーです。そこそこ小綺麗であれば何の差し障りもない、というのが地球上の全生物におけるアプリオリな共通認識でもあります。
僕らはイカす人々に対してじぶんたちが不足の側にあるような印象を抱きがちだけれども、実際には逆であることを、意識せず受け継いできた言葉が諭すように教えてくれている、稀有な事例のひとつと申せましょう。
したがって、質問のお答えとしては「そうでないほうが自然だから!(強調)」ということになります。
*
ちなみに僕は若いころ、洒脱、洒落、瀟洒といった似たような意味合いの単語について、なぜ抜けたり脱したりしているのかではなく、なぜ酒が含まれているのかという疑問を抱いたことがあります。そこでびっくり仰天したのは、これらの単語に含まれる漢字が酒ではなく洒だったことです。
酒はさんずいに「酉(とり)」、洒はさんずいに「西(にし)」です。酒はもちろん酒のことですが、洒は洗い清めるとか、すすぐと言った意味があります。
つまり洒脱にしても洒落にしても、要は2文字合わせて「きれいさっぱり」を表していたわけですね。
エヘン、とドヤ顔で語り散らしていますけれども、字が違うことに長年気づいてなかったの、僕だけだったらすみません。
A. そうでないほうが自然だからです!(強調)
*
質問はいつでも24時間無責任に受け付けています。
dr.moule*gmail.com(*の部分を@に替えてね)
その473につづく!
2026年2月20日金曜日
ムール貝博士のパンドラ的質問箱 その471
キング昆布さんからの質問です。(ペンネームはムール貝博士がてきとうにつけています)
Q. つい先日、何の気なしに見たドラえもんの映画『のび太の地球交響曲』がとてもよく24年間で一番感動した映画のひとつとなりました。あらすじとしては音楽会でリコーダーを練習するのび太の前に音楽を消してしまうアメーバが表れ仲間たちが音楽を使い退けるというお話で劇中にはクラシックの有名曲や音楽家が登場して.....etc
大吾さんは今まで見た映画(子供向け作品)で衝撃を受けた事はありますか?
いいですね。映画にかぎらず何であれ良い作品というのは大人と子供を区別しないものだけれど、それを実感する機会ってじつはそんなに多くありません。ドラえもんとか、アンパンマンとか、クレヨンしんちゃんとか、明らかに子ども向けとわかる作品の場合、それだけで僕ら大人は自身を対象外とみなしてしまうし、そもそも世の中には子ども向けでない作品のほうが圧倒的に多いので、どうしても優先度が下がります。
もちろん、子どもといっしょであれば自然とそうした作品にふれることになりますが、ただ個人というよりは「子の親」として接することになるので、そこから自身のオールタイム・ベストにまで昇格することはやっぱり多くないでしょう。そういう意味では、あくまで自分自身が自分自身のために観た劇場版「ドラえもん」がオールタイム・ベストのひとつに加わるというのはまちがいなく得難い経験です。その後の人生における選択肢が増えると言っても過言ではありません。
そういえば劇場版クレヨンしんちゃんの中でも屈指の名作として語り継がれる「クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲」の公開が2001年なので、ちょうど僕もキング昆布さんと同じくらいの年齢でした。(1)子どもの頃に観るのと、(2)大人になってから観るのと、(3)親になってから観るのとではそれぞれ感慨がちがう(のに評価は変わらない)らしいので、機会があったら観てみてください。平成前期から昭和を振り返るかんじなので、令和の今からしたらまたちょっと印象が変わるというか、さすがにちょっとアレかもしれないですけども。
あと、そうですね、衝撃を受けるとなると、感動以外にもいろんな側面があります。
たとえば、古川耕さんに教えてもらった劇場版「デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム!」は、表現や演出がとにかく洗練されていて度肝を抜かれました。公開は先のクレヨンしんちゃんと同じく四半世紀前なので、今も同じ衝撃を受けるとは言えませんが、でもすごかった。ちなみに監督は今やすっかり重鎮となった細田守さんです。
それからこれはわりと最近ですが、スポンジ・ボブの劇場版「スポンジ・オン・ザ・ラン」ですね。3Dアニメですが、実写ゲストとしてキアヌ・リーヴスとスヌープ・ドッグが出演しています。酒場の常連としてラップするスヌープもめちゃカッコいいんだけど、キアヌ・リーヴスに至ってはなんと「草」の役です。草ですよ!
何言ってるかわからないと思われることは僕も重々承知しています。でも草としか言いようがない。ストーリーの上ではスヌープより圧倒的に重要な役回りなので、言ってみれば主人公であるボブたちを導く賢者的な立ち位置ですが、見た目は草です。回転草(tumbleweed)という、アメリカ特有の転がる枯草を、キアヌが演じています。演じるというか何というか、まあ演じてるんだけど、あるだろもっとこう、やり方とか、魅せ方が他に!というかんじで雑なんですよね。いい意味で。いや、悪い意味か?どっちだ?
A. 「スポンジボブ:スポンジ・オン・ザ・ラン」です。
*
質問はいつでも24時間無責任に受け付けています。
dr.moule*gmail.com(*の部分を@に替えてね)
その472につづく!
2026年2月13日金曜日
ムール貝博士のパンドラ的質問箱 その470
ハーバード大学芋さんからの質問です。(ペンネームはムール貝博士がてきとうにつけています)
Q. 年末で家の前の木が4本切られ、景色が変わりました。一番良い休日の使い方はなんですか。
うちにはかつてお隣に2軒並んでいて、それぞれ趣の異なる古い民家でした。一軒は庭がとても広くて、じつに見事な桜の大樹があり、春になるとうちの窓から桜の花びらが吹雪のように吹きこむという、それはそれは夢のような風情があったものです。桜の幹には区の保存樹木というプレートが付いていたので、この先もずっと大事にされていくんだろうな、と思っていたらあるときあっさり根元から伐り倒されてしまいました。土地まるごと売却されたら保存もへったくれもないのかもしれません。立派なお屋敷も取り壊され、更地になり、今は6軒の戸建てと軽量鉄骨のアパートが建っています。23区内にしてはなかなか広い土地だったことがよくわかりますね。
もう一軒も土地としてはかなり大きめだったのだけれど、庭というよりもむしろ鬱蒼とした背の高い雑木林の中にあばら家がぽつんとあって、完全に日当たりゼロという、なんだか魔女の家みたいな印象でした。今となってはすっかり見かけなくなったバキュームカー(!)がたまにきていたので、2010年くらいまでトイレが汲み取り式だったことになります。このあたりでは最後の生き残りだったとおもう。
これはたしか昔ブログにも書いた気がするけれど、あるときうちのベランダからハンガー(クリーニング屋さんでもらってくる針金のやつ)が毎日のように消失する事件がありました。はてなと首を傾げながらふと雑木林を見上げると、ずいぶん高いところに色とりどりのハンガーで作られたカラスの巣があり、絶句した記憶があります。カラスの巣を見たのも、それが異様にカラフルなことも、そしてその材料が全部ハンガーだったことも、その巣に小さな雛鳥がいたことも、何もかもが初めて見た光景だったので、忘れられません。そんな魔女の家も今はなく、めちゃおしゃれなマンションになっています。なのでベランダからの視界にはコンクリートしかありません。
一番良い休日の使い方は、そうですね、休むことだと思います。休む日と書いて休日ですからね。
休日というのは言ってみれば何をするのも自分で決めてよい自由行動日でもあるので、いかに楽しく有効活用するかという観点でつい考えてしまいがちだし、それはそれでまちがってはいないけれども、一方でそれはともするとある選択が得で、そうでないと損という損得勘定に転じかねません。目が覚めたら夕方で1日をムダにしたと感じるのはまさにその典型です。
しかし休日にしかできないことをしたという点ではどこかに出かけて欲望を満たすこととじつは完全に等価でもあります。休日という字義にも過不足なく合致している以上、むしろごろごろと寝過ごすことのほうがよっぽど本来のあり方であると申せましょう。僕なんかは対価の生じる業務を除いた人生のあらゆる局面において、ムダにこそ豊かさがあると考えているくらいです。
A. 気が済むまで存分に休むことです。
*
質問はいつでも24時間無責任に受け付けています。
dr.moule*gmail.com(*の部分を@に替えてね)
その471につづく!
2026年2月6日金曜日
ムール貝博士のパンドラ的質問箱 その469
ちいかわの流れのようにさんからの質問です。(ペンネームはムール貝博士がてきとうにつけています)美空ひばりの幻の名曲ですね。
Q. 好きな響き、発音の言葉はありますか?意味や字面は考えないで、純粋に響きや発音した時の舌触りが好きな言葉です。自分は"枯淡"=コタンです。漢字や意味で考えると侘しさがありますが口の中で転がっていくような感触に愛嬌があり気に入っています。
日常で使うことはこの先たぶんないだろうな、と心の引き出し奥にしまいこんでいた言葉を、とうとう引っぱり出すときがきましたね……。僕にとってそれは「枢」です。「くるる」と読みます。
可愛い〜!
何となく物々しい漢字の字面に対して、くるるという超無害な読みは、そうですね、映画「マッドマックス:フュリオサ」で筋骨隆々の恐ろしいディメンタス将軍が大事に持っていたちっこいテディベアを彷彿とさせます。
僕は元来ギャップというか相反性を人生における喜びのひとつに位置づけ、目にするたびにいちいち悶絶する気質の男ですけれども、これは文字と言葉でも同じように心くすぐられることがあると気づかせてくれた一語です。
そういう意味では、枯淡(こたん)もそうですね。いつもは気難しい頑固な老人が赤子に頬をゆるめて「よちよち」とあやすのにも似た味わいがあります。
ちなみに枢というのは昔々、まだ蝶番が存在しなかった時代からある、伝統的な開き戸(扉)の一部を指します。具体的には、戸の右端もしくは左端の上下に軸をつけて、この軸を受ける穴に差し込むことで戸が回転式に開閉できるわけですね。この軸(戸の上下にある出っ張り)もしくはこの機構全体を指す、それがつまり枢です。
その用途からしてすでにくるる感溢れることにまたキュンとさせられます。実際、くるんてなるための部分ですからね。そのまんますぎてちょっと照れくさい印象を、あえて鯱張った漢字でカバーするあたりもポイントが高い。キャラクターとして完成されている、と言ってもよいでしょう。ぬいぐるみやアクスタが飛ぶように売れる何らかの未来が思い浮かぶようです。
そして枯淡と同じく、音としても心地よい点こそ重要です。転がるような、螺旋を描くような、そして口の中でいつまでも味わえる印象があります。枯淡よりもはるかに使用頻度の低いと思われることがもどかしくてなりません。うちにある古い茶箪笥には、蝶番でなくこの枢で開く戸が実際についていますが、さすがにこれを一般的と言うことはできますまい。というかそもそも茶箪笥って何だよとツッコまれる可能性のほうがたぶん高い。
シンプルな構造の名称なので、絶滅はしないかもしれないけど、今となっては永遠に絶滅危惧種である、とは言えそうな言葉です。
「ほとんど見かけないけど原始的な戸の出っ張り部分」にこの愛らしい名がついている、という事実もなんというか、ちょっといいんだよな〜。
僕としては言葉としても、また実際に戸としても、見かけたらラッキーみたいな、幸運の象徴でもあります。コロボックルに近いよね。
A. 枢(くるる)です。
*
質問はいつでも24時間無責任に受け付けています。
dr.moule*gmail.com(*の部分を@に替えてね)
その470につづく!
2026年1月30日金曜日
ムール貝博士のパンドラ的質問箱 その468
フローリングストーンズさんからの質問です。(ペンネームはムール貝博士がてきとうにつけています)床に転がる石ですね。
Q. 眼鏡はかけたままお風呂に入りますか?
そうですね、シャワーを浴びるときの眼鏡、顔を洗うときの眼鏡、髭を剃るときの眼鏡、髪を洗うときの眼鏡、体を洗うときの眼鏡、湯船につかるときの眼鏡があり、ちょっとずつ必要な度数がちがうのでその都度使い分けています。とくに顔を洗うときなんかはめちゃめちゃ邪魔ですが、鼻が邪魔だからといって削ぎ落とすわけにもいかないのと同じ理由で、しぶしぶかけています。
眼鏡にしてみれば頼んでもいないのに泡まみれにされることに強い疑念を抱かざるを得ません。ふとした折にこう呟くこともあるでしょう。「なんでおれだけがこんな目に遭わなくちゃいけないんだ?」
「待ってくれ、それを言うなら」と髭を剃るときの眼鏡が言います。「僕は髭を剃るときの眼鏡だけど、それはもちろん剃るべき髭をよく見るためだ。でもよく考えてみると、髭なんか見なくたって手触りで剃れるじゃないか?百歩譲って必要だとしても、僕が見せるものと言ったら鏡に写る髭だけだ。想像してみてくれ、こんなに世界は広いのに、明けても暮れても目の前にあるのはむさくるしい髭だけなんだぞ!なんでこんな目に遭わなくちゃいけないのかだって?それは僕こそ言いたいよ!」
「待って待って、それを言うなら」と髪を洗うときの眼鏡が言います。「髪を洗うのに眼鏡はいらなくない?」
「そんなことはない」と体を洗うときの眼鏡がいいます。「シャンプーとかコンディショナーとかボディソープを判別するのに必要なはずだ。君には君の役割がある。わたしを見ろ、石鹸なんか他の何とも間違えようがない。だとすれば体を洗うのに眼鏡は不要なはずじゃないか」
「さっきじぶんでボディソープって言ってなかった?」と湯船につかるときの眼鏡が言います。
「ボディソープとシャンプーをまちがえるのはよくないね」と髭を剃るときの眼鏡が言います。「つまり体を洗うときにも眼鏡は必要なんだ」
「とはいえ石鹸なら間違えることもないから…」と髪を洗うときの眼鏡が言います。「眼鏡としてのレゾンデートルを維持するためにはなんとしてでもボディソープを使ってもらう必要があるってこと?」
「待ってくれ、よく考えてみたら」と顔を洗うときの眼鏡が言います。「顔を洗うのに眼鏡がいるのか?何を見るって言うんだ?」
「それはさっきも話してたが」と体を洗うときの眼鏡が言います。「だからと言ってかけないわけにもいかないんだよ。眼鏡を支える鼻と耳が、匂いを嗅ぐことと音を聞くことしかできなくなったらどうするんだ?」
「問題なくない?」と髪を洗うときの眼鏡が言います。
「あれっそういえば」と髭を剃るときの眼鏡が言います。「湯船につかるときの眼鏡は何を見てるの?」
「何も見てないよ」と湯船につかるときの眼鏡が言います。「見てるようで、何も見てない」
「それでいいのかい」と髭を剃るときの眼鏡が言います。
「いいよ、もちろん」と湯船につかるときの眼鏡が言います。
「なんで?」と髭を剃るときの眼鏡が食い下がります。「だってそれは…」
「かけなくてもいいってこと?」と湯船につかるときの眼鏡が言います。「そうかもね。でもかけてる」
「そこがおかしいんだ」と顔を洗うときの眼鏡が言います。「なぜかける?」
「かけたいからでしょ」と湯船につかるときの眼鏡が言います。「みんな一体何の話をしてるの?」
「何って…」と顔を洗うときの眼鏡が言い淀みます。
「それは…」と髭を剃るときの眼鏡が口ごもります。
「君はどうなんだ」と体を洗うときの眼鏡がシャワーを浴びるときの眼鏡に尋ねようとあたりを見渡します。「あれ?」
「帰ったよ」と湯船につかるときの眼鏡が言います。「もう眠いって」
「髪を洗う眼鏡もいないぞ」と顔を洗うときの眼鏡が気づきます。「さっきまでいたよな?」
「デートでしょ」と湯船につかるときの眼鏡が言います。「ずっとソワソワしてたもんね」
…というような話だったらよかったんだけど、残念ながら僕は眼鏡をかけたまま風呂に入ることはありません。温泉とかスーパー銭湯くらい広いとさすがに危ないのでかけます。またその場合、湯船につかるときもかけていますが、これは視力の補助というより、単なる収納として耳と鼻に引っ掛けているだけです。うっかり踏んづけたり、どこかに置いてきてしまう心配がないし、なんと言っても持ち運ぶのにちょうどいいですからね。
A. かけません。
*
質問はいつでも24時間無責任に受け付けています。
dr.moule*gmail.com(*の部分を@に替えてね)
その469につづく!
2026年1月23日金曜日
全身の細胞たちがスタバでリモートワークに勤しんでいること
僕は極度の寒がりで、気温が10度を下回れば途端に身体機能が低下して、人というよりはむしろ路傍の枝に近くなる男ですが、しかしよくよく考えたら昔のほうが今よりもずっと寒かったはずだ、とふと思うのです。
何しろ防寒着というものがありません。あるとしても素材は毛皮、真綿、木綿くらいのはずです。そのどれもユニクロで買えるような手軽さではないし、当然ヒートテックほどの保温力もありません。
火に関して言えば昔も今も最強だし、木炭という至高の知恵も含めて今よりもよっぽど人々の暮らしに寄り添っていたと思いますが、ライターやマッチほどイージーな着火もできないばかりか、そもそも日本は家屋の風通しが必要以上に良すぎたので、空間として温まることもあまりなかったでしょう。風呂だってまず水を汲んでくることから始まる大昔では当たり前には望めますまい。
今を生きる僕でさえ、子どものころ祖父母の家に泊まった時の布団の冷たさを覚えています。寝たくない理由のひとつにその冷たさがあったくらいです。
つまり総じて、ずーっと寒い。少なくとも肌が外気にふれる割合は、どう考えても今よりもずっと大きい。僕なんかはそれを想像するだけで気を失います。
ただ体感としては、寒がりのプロフェッショナルである今の僕と同じように感じることもなかったでしょう。机の前に座ってただ手を動かすだけなんてことはほとんどなかったし、何をするにも常にせっせと全身を動かしていたはずだからです。代謝は今よりもずっと活発だったとおもう。
つまり僕らがこんなに寒いのは、大昔に比べて体を動かすことが圧倒的に少ないから、ということになります。現代における運動不足は誰でも痛感するところだとおもいますが、それ以前の問題です。指一本で部屋を温めたり風呂を沸かすことができてしまう時代である以上、移動や家事以外に体を動かすことがあまりないとさえ言えるでしょう。極論すればそれでもなお常に温かくいられるから、ということです。
加えて、防寒着は防寒着でとんでもない進化を遂げています。これを着ていれば寒くないという選択肢が無数にある時代です。
体をあまり動かす必要がなく、かつ防寒着がいくらでもある環境であれば当然、寒さを感じる閾値はめちゃめちゃ低くなります。かつては奴隷のようにせっせと働かされていた非力な細胞たちがスタバでコーヒーを啜りながらリモートでデスクワークをしているようなものです。寒いわけだよ、と言うほかありません。
したがってこの寒さ、具体的にはその体感を最小に留めようとするならば、まず防寒という要素を片っ端から脱ぎ捨てる必要があります。暖房器具やもちろん、衣服さえパンツ以外は問答無用で焼却です。最後に暖を取るのはこれを燃やす火ということになるでしょう。僕は独裁者として、配下である全細胞に働けと命じます。なんとしても凍死する前に代謝をフル稼働させなくてはなりません。やがて寒さを感じなくなるのは十中八九まちがいないですが、それが温まったからなのか死にかけているだけなのか、それは神のみぞ知るです。
池袋近辺で打ち捨てられている素っ裸の亡骸を見かけたら、ねんごろに弔ってやってください。たぶん僕です。
登録:
コメント (Atom)