ていねいなクラッシュさんからの質問です。(ペンネームはムール貝博士がてきとうにつけています)
Q. 生チョコ、生キャラメルをはじめ、生食パン、生ドーナツ、生クッキー、果ては生タピオカや菌床生しいたけなど、近年いろんなものが「生」になっている気がしています。大吾さんは、この「生」ブームに最後まで抗える(「生」化しない)のは何だと思いますか?私は今のところ「焼き芋」が強そうだなと考えています。
さりげなく生しいたけが紛れこんでいるのがいいですね。僕も以前、なぜわざわざしいたけに生とつける必要があるのか疑問におもったことがあります。柿や大根だって干すのに、干さないものを生柿とか生大根と呼ぶことはないからです。
それで知ったのだけれど、じつはしいたけに限らず、きのこが生のまま流通するようになったのはわりと最近のことで、僕が生まれたころでさえ、今ほど当たり前ではなかったらしいんですよね。しめじなんかもひょっとしたら70年代にはまだ八百屋には並んでいなかったかもしれない。
ただしいたけに関してはそれよりもはるかに昔から干して使われていたので、干してないことを強調するために生と呼んでいたのがそのまま定着したんだとおもいます。それまで干したものしかなかったのなら、じっさい僕でも「おい!しいたけだ!ちげーよ、生だぞ!」と騒ぐ気がする。
あだしことはさておきつ…
そういえばあまり聞かなくなった気もするけれど、生チョコを初めて食べたときのちょっとした感動は忘れられません。むかしむかし、一人暮らしをしていたころ、バレンタイン商戦でにぎわう駅ビルに入り、せっかくだからチョコでも買って帰ろうとガラスケースをのぞきこみ、思いのほか高価なことに驚きつつ小さめのをひとつ買って、アパートの薄暗い6畳間でひとりもぐもぐ食べました。ほんと鮮明に覚えてるから、よっぽどおいしかったんでしょうね。もしタイムマシンであのころに戻れたら、お前は人生の味わい方をよくわかってるなとじぶんを褒めてやりたい。
ともあれ、生という理由でトレンドに上がるのはやっぱりスイーツ系ですよね。生てんぷらとか生コロッケは言われても食欲をそそりません。生パスタには付加価値があるのに、生うどんにはありません。生食パンはいけるのに、生おむすびはむしろ剣呑です。生と付けられそうな条件をいろいろ考えてみたものの、ぜんぜんわかりませんでした。言葉のあり方としてもちょっと考えてみたいトピックです。
いま挙げたどれも「生」には抵抗できそうですが、お題の主旨としてはなんとなく違うことは僕もわかるので、ここはあえてスイーツ系に限ってみましょう。焼き芋なんかもギリスイーツですもんね。あれこれ考えれば考えるほど食パンの存在が邪魔くさいんだけど、こいつはもう放置するほかありません。
生チョコ、生キャラメル、生ドーナツなんかに共通するのはおそらく、本来よりも口当たりがとろけるようにやわらかい点です。
そして仮に技術革新で焼き芋がスイートポテトよりも「やわとろ」になった場合、意味に頓着しない日本人としては平気で「生焼き芋」と名付けるはずです。こういう節操のなさには正直、確信がある。したがってあくまでこの「生」に抗うとしたら、それなりの固さを保つものよりもむしろこれ以上やわらかくなりようがないスイーツを挙げます。たとえばシュークリームとかゼリーです。
とおもってググったらどっちもすでにあって横転しました。日本語における節操のなさが図らずも証明されて頭を抱えざるを得ません。フルーツが生とかクリームが生とか、初めっからだろうが!!!コレステレロールなんか初めから含まれてないサラダ油にわざわざ「コレステロールゼロ」とかさも特別みたいに表記してんの意味わかんねえなと思ってたけど、完全にそれと同じレベルじゃないか。
もういい、じゃあガムにします。やんなっちゃうな、ほんとにもう。
A. ガムです。
しかしこういう文脈における「生」、感覚的にはすごくよくわかるしいずれ辞書にも載りそうな用法という気がするんだけど、どうやって定義したらいいんだろう。
*
質問はいつでも24時間無責任に受け付けています。
dr.moule*gmail.com(*の部分を@に替えてね)
その464につづく!
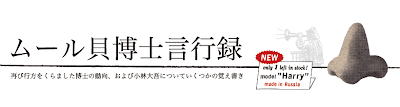

0 件のコメント:
コメントを投稿